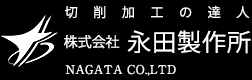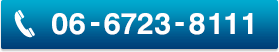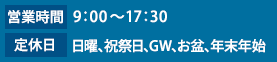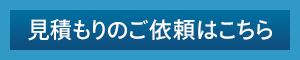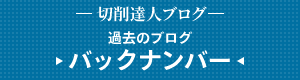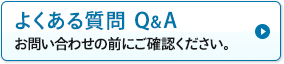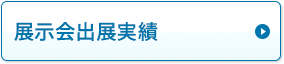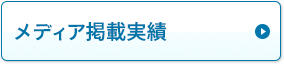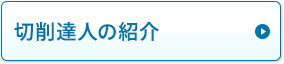「切削達人」集団 株式会社永田製作所 広報 永田菜々です。
ついに、プロ野球が開幕しました。 プロ野球観戦が趣味の私は、開幕するとテレビで試合を見たり、球場に足を運んだりと少し忙しくなります(笑)
私が、野球を好きになったのは小学4年生の時にソフトボールを始めたからです。
その時学校で配布された無料観戦チケットがあり、勉強のために球場まで観戦に行ったのがきっかけです。
気づけば好きな球団ができ、休日は母と球場まで野球を見に行ってました。
まったく野球やソフトボールに興味がなかった母ですが、私の為に球場に連れて行ってくれたり、 私の試合がある日は必ず応援に来てくれました。
母は、試合で勝った日はすごく褒めてくれ、負けた日は慰めてくれました。 いつも怒ることなく応援してくれていたのですが、一度だけものすごく怒られた試合があります。
小学6年生の春、近くのグラウンドで新人戦が行われました。
ひとつ上の学年にピッチャーがいなかったこともあり小学5年生からエースとして投げていた私は、 かなり試合慣れをしていました。
相手は、普段よく試合をしたことがあるチーム。仲間も調子がよく前半はリードしていました。

しかし、前半まではなかなかバットに当たらなかった相手が慣れだしたのか、ヒットが続きました。
相手の保護者の歓声が気になり、次第に集中力が無くなりなかなかストライクが入らない様に…
気づけば、逆転されその試合は負けてしまいました。
試合後、泣く私に母は言いました。
「一人でやっているんじゃない。もっと周りを見なさい」 私一人が頑張れば、勝てると思っていたけど今回は私が試合を台無しにした。
そこからです、自分ひとりで頑張ろうと思わずに周りへの声掛けを意識し始めました。
チームスポーツの大切さをまだわかっていなかった私に、母が厳しく言ってくれたおかげでみんなで勝つ という楽しさを知ることが出来ました。
この出来事が私のソフトボール人生の原点でした。