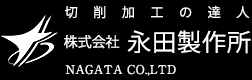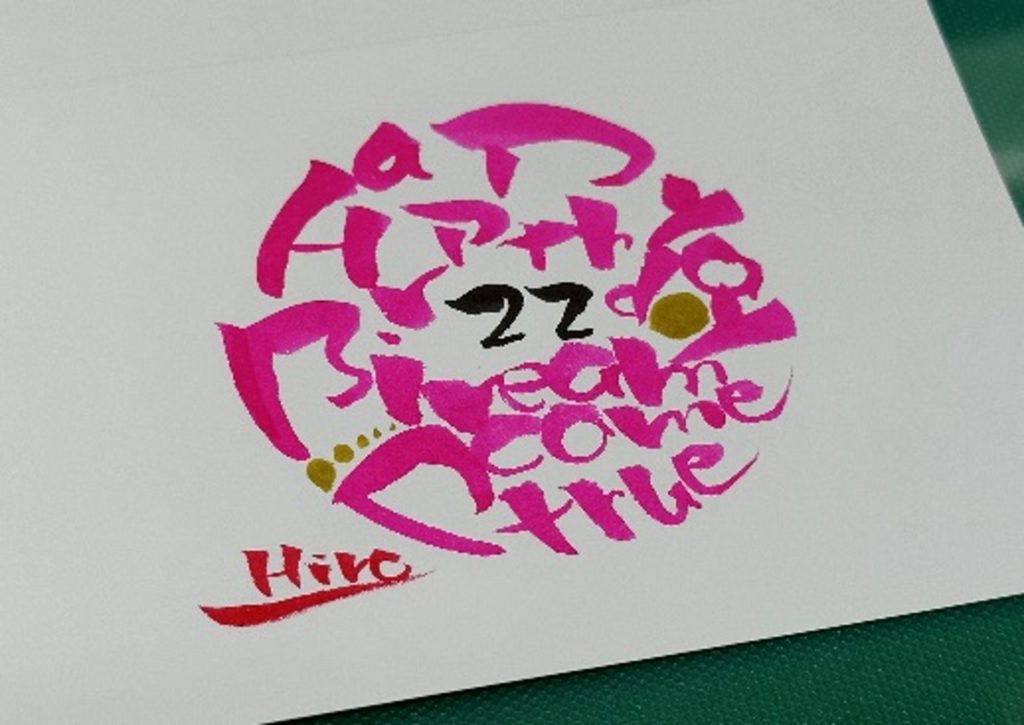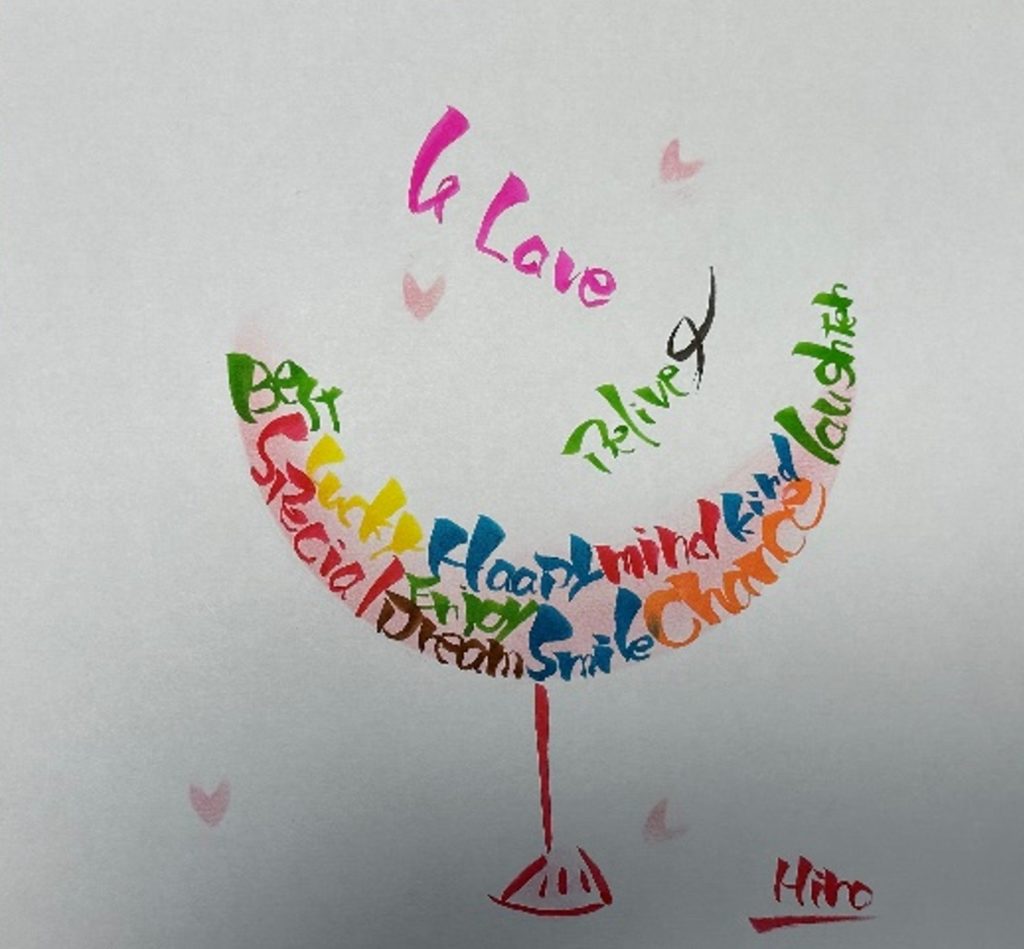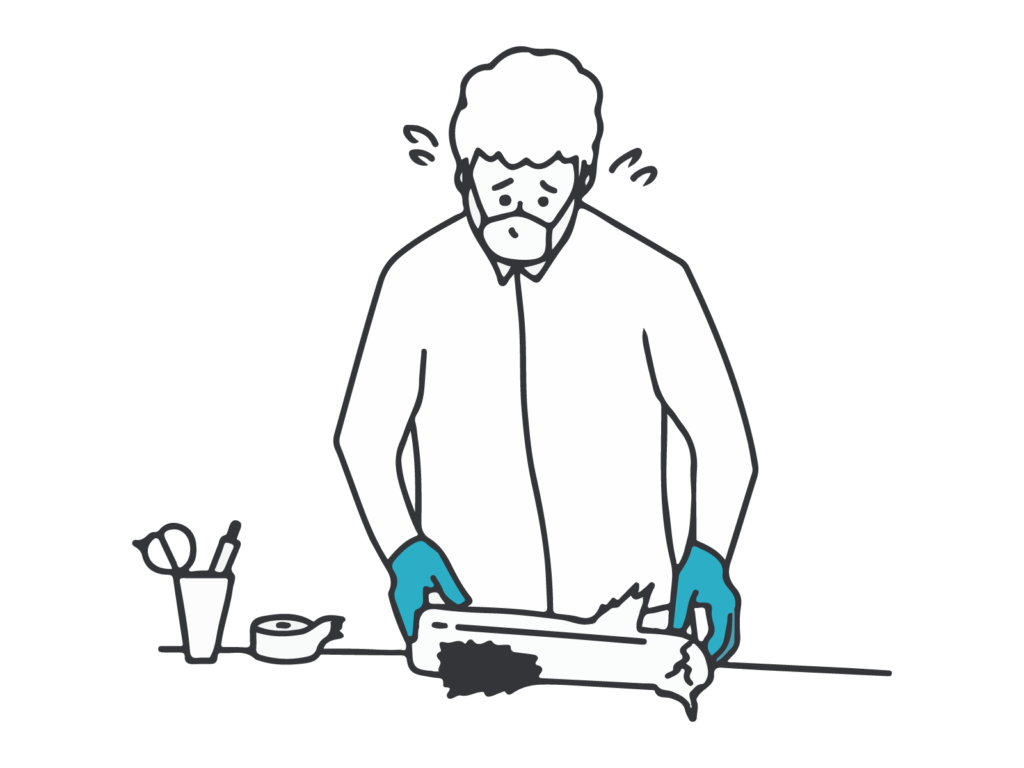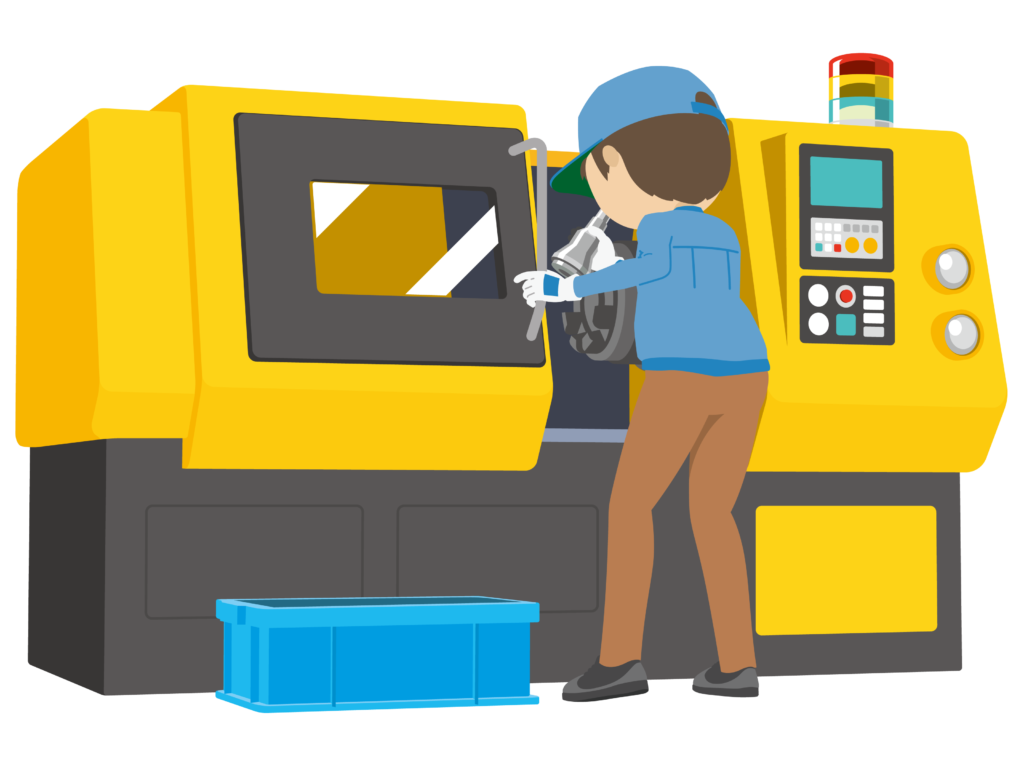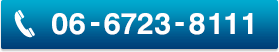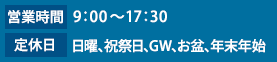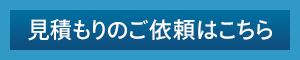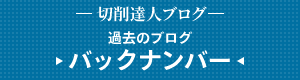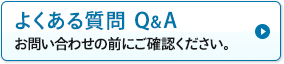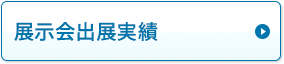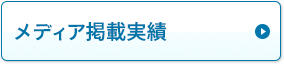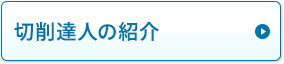モノづくりの街東大阪から「新たな風を吹かします!」株式会社永田製作所 広報の永田菜々です。
1月19日、大阪市中央会堂で開催された「あきない新春特別セミナー2024」に参加しました。
約50名の方々が、全国各地から集結しました。

ー講師について
ライソン株式会社から、代表取締役 山様・広報 三上様・動画クリエイター 佐藤様の3名に加えNNA株式会社 佐藤先生が登壇され、それぞれのテーマに合わせて講演されました。
ー数々の大ヒット商品を発売
・第一部 ライソン株式会社 代表取締役 山俊介様
数々の大ヒット商品を販売しているライソン株式会社。
店頭で一度は見たことのある製品の制作の裏側をお話いただきました。
山社長が製品を作るうえで大切にしてる『この商品を買う一人のお客さまのことだけを考える』というお話で、私は世間が欲しいものを作ることこそが家電メーカーの役割だと思っていました。
ですが、他社にない製品で差別化をすることで独自のポジションを築き上げてきたそうです。
私の中の常識が覆った瞬間でした。思わず、「なにこれ!」と手に取ってしまう製品だからこそ大ヒットしたのだと感じました。
ー広報の役割って?
・第二部 ライソン株式会社 広報 三上紅美子様
2023年9月に入社し、何の経験もない私が広報担当になりました。
就任したものの、広報の仕事というものをあまりわからず、過ごしていました。
弊社は、以前に情報番組に取り上げられたことがありますが、ここ数年は特にありません。
メディアに取り上げる方法やメリットをたくさん紹介していただき、広報の役割が明確になりました。
まずは、とことんやってみる!広報のこれからに注目していただきたいです。
ー登録者数40万人以上!
・第三部 動画クリエイター 佐藤大将様
今や、大人気YouTuberの佐藤さんですが、初めはなかなか思うようにいかなかったそうです。
苦悩した過去や、YouTubeに対する熱い思いを聞くことができ、私ももっと頑張ろうと思いました。
宣伝しない宣伝方法で、今まで誰もしたことのない動画だったからこそ今の登録者数に繋がっているんだと感じました。
写真も撮って頂きありがとうございました!

ーまとめ
・第三部 NNA株式会社 佐藤元相様
コロナ前とコロナ後の営業のやり方の変化をお話いただきました。
時代に合わせたやり方こそが大切だと感じました。
最後に、アクションプランを作成しました。これから、自身が取り組んでいくことをまとめていきました。
一日で、すごい情報量が入ってきて頭から湯気が出っぱなしでしたが、何が必要か、何からすべきなのかを整理して、取り組めることから始めていきたいと思います!
ライソン株式会社様、企画・運営していただいたNNA株式会社様 ありがとうございました!!